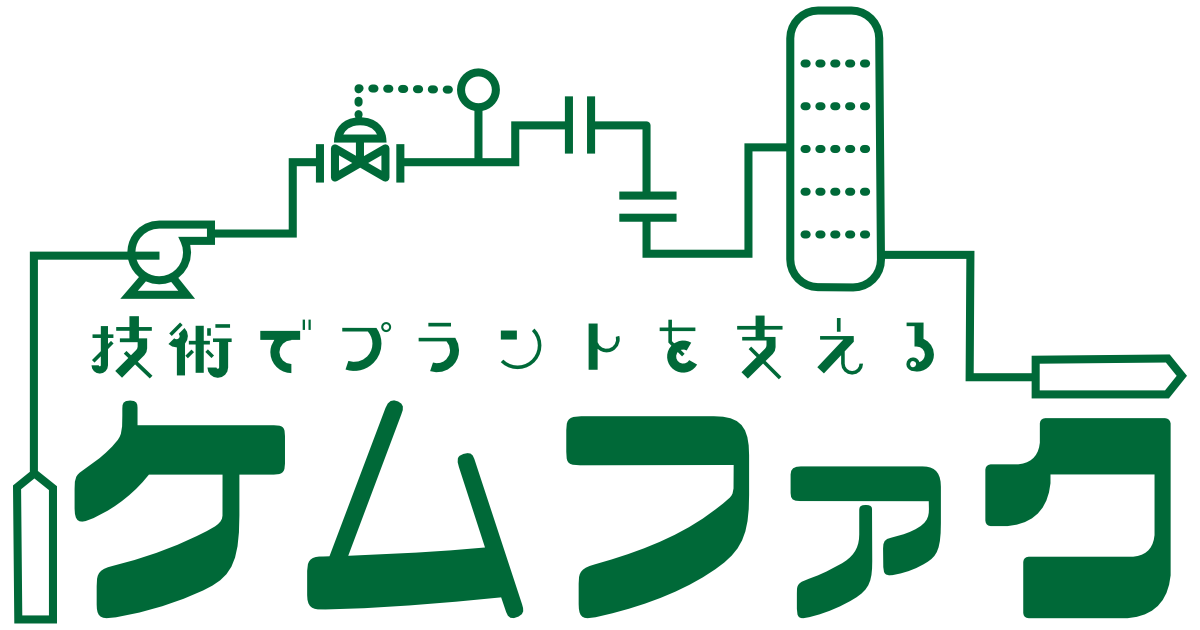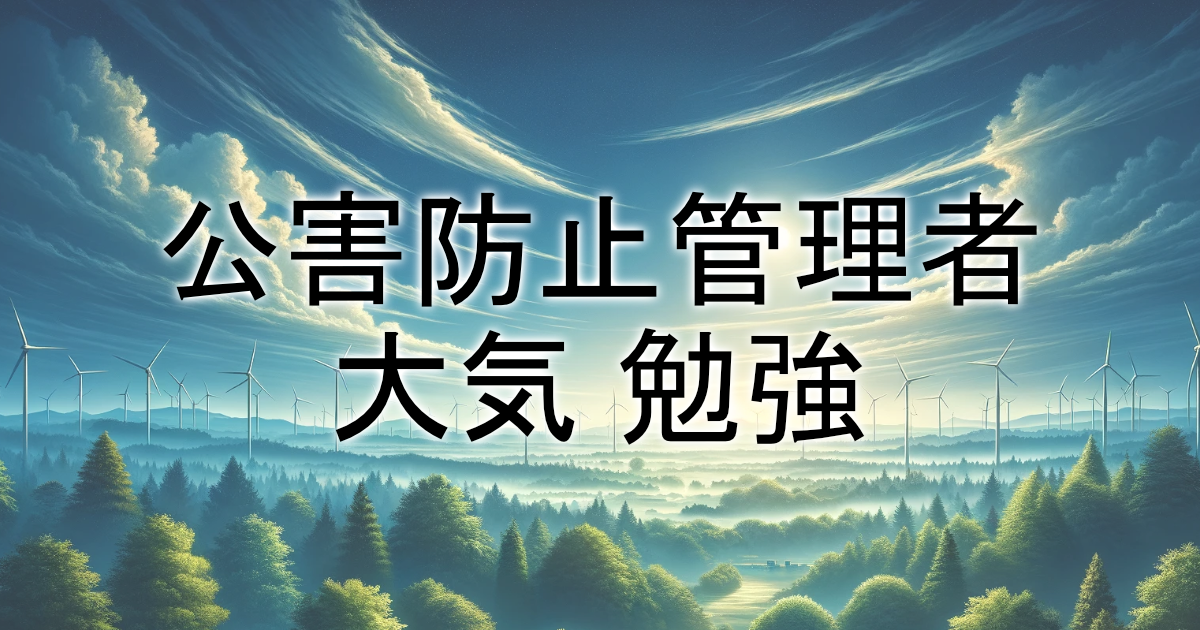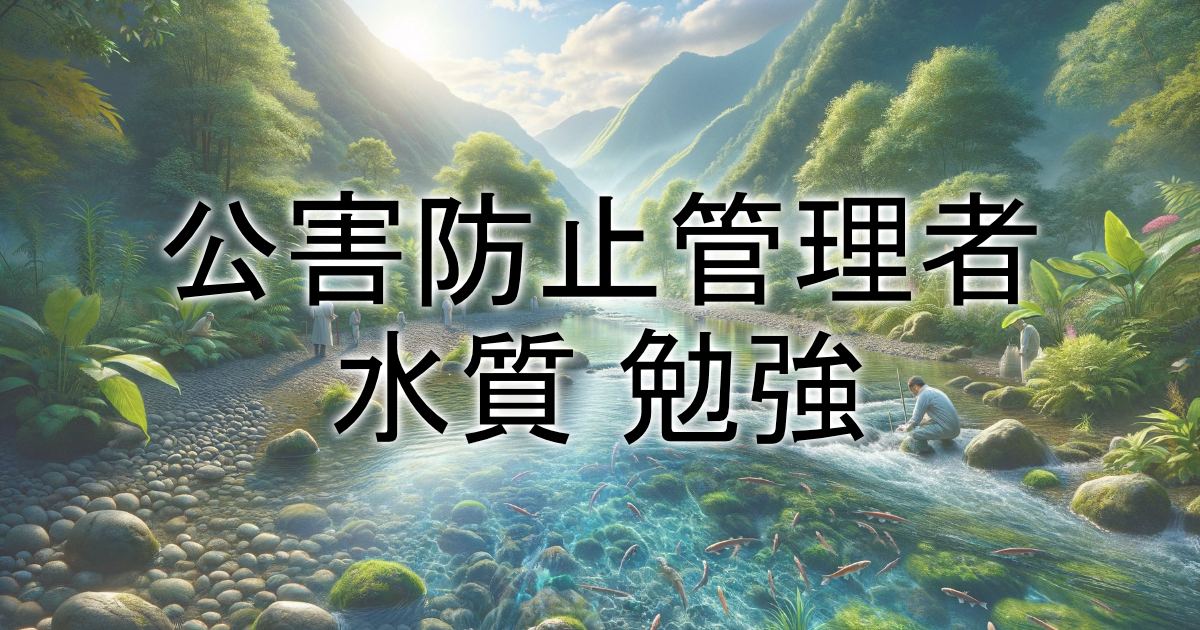試験の合格率は20~30%程度、一発合格者に絞れば合格率は10%以下です。
過去問の勉強は「公害防止管理者試験まとめました」というサイトがオススメです。
参考書は、安全に合格したい場合や不安な場合は迷わず購入しましょう。
勉強にあたり意識しておいて欲しいのは以下の点です。
- 丸暗記しない:定期的に出題傾向が変わってしまう
- 法令は読んでおく:原文を埋めることも多い
- 公式は覚えておく:式から回答を絞れる場合がある
- 工場の設備を見ておく:公害発生源や処理設備の話も多い
公害防止管理者の試験の教材になりそうなサイトは以下にまとめましたので活用してください。
筆者の受験成績
まずは私が受験した際の結果について記載します。
大気1種は6科目一発合格
大気1種は一発合格しました。
初めての公害防止管理者試験でしたので公害総論も含めて6科目全て受験しました。
水質1種は惜しくも後1点
水質1種は2回目で合格しました。
大気1種合格後のため公害総論を免除し4科目の受験です。
1回目は汚水処理特論・水質有害物質特論・大規模水質特論に合格、水質概論は1点足らずで不合格でした。
2回目で水質概論に合格しました。
試験難易度
公害防止管理者の試験は想像よりも難易度が高いです。
一発合格者は10%程度
公害防止管理者は範囲が広く科目数が多いことが特徴で、科目合格を狙う方も多くいらっしゃいます。
合格率は20~30%程度と難易度は高めです。
この合格率は「一発合格者」と「科目合格者のうち全科目合格達成者」の両方が含まれています。
一発合格者に絞れば合格率は良くても10%程度です(参考資料:公害防止管理者制度とデータでみる公害防止管理者の現状)。
100時間以上の勉強時間
この試験は事前知識の量によって勉強時間が左右されます。
いくつかのサイトに参考時間が記載されており、最低100時間は勉強する必要があります。
過去問以外の勉強が必須
半分程度は過去問と同様の問題が出題されます。
残り半分は過去問の内容を避けるような細かい内容が出題されます。
分からない問題の推測がカギ
この試験の難しい理由は「予想だにしない方向からの出題」と「重箱の隅をつつくような問題」にあります。
過去問だけでは十分にフォローできません。
対して教科書全て読み込んで覚えるなんて話は現実的ではありません。
公害防止管理者試験では分からない問題に対して自身の知識をフル動員して予測することがカギとなります。
勉強方法
自身の経験を基に、試験の勉強方法を紹介します。
向き不向きもあると思いますが、少しでも参考になれば幸いです。
過去問
過去問の勉強は「公害防止管理者試験まとめました」がオススメです。
過去問が10年分以上も載っていますので、すべての年代・科目において点数が9割取れるように試験を繰り返します。
※9割と設定しているのは、試験年度から3年前の数値を問うことが多く過去問の場合そこだけ正しい回答ができないためです。
参考書
購入したのは大気1種、水質1種どちらもオーム社の合格テキストのみですが、既に販売が終了しています。
代わりとしてTAC出版の「公害防止管理者 超速マスター」が同様の構成・内容になっておりオススメです。
また公式テキストは高価でありボリュームが大きいため購入していません。
振り返ると余計な調べ物をしてしまった印象もありますので、安全に合格したい場合や不安な場合は迷わず購入しましょう。
参考サイトまとめました
公害防止管理者の試験の教材になりそうなサイトは以下にまとめましたので活用してください。
法令
ほぼ100%出題されると言っても過言ではない環境基本法をはじめ、以下の法令に関しては全ての条文を読むことをオススメします。
試験直前まで読んで確実に回答できるようにすべきです。
- 環境基本法
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
- 大気汚染防止法(大気1種)
- 水質汚濁防止法(水質1種)
環境基本法第2条の定義に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
この法律において(1)「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の(2)気候変動又はオゾン層の破壊の進行、(3)海洋の汚染、(4)野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす(5)事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
R5 公害総論 問1
環境省のサイト
補足資料として各省庁(特に環境省)からの情報を参考にしています。
共通項目として「総合環境政策」、大気1種は「大気環境・自動車対策」、水質1種は「水・土壌・地盤・海洋環境の保全」のページを確認しておくことをオススメします。
少なくとも概要やまとめの資料だけでも目を通してください。
計算問題、公式
計算問題は決まった形式が出題されることが多く、確実に解けるように練習を繰り返していました。
それでも考え方は十分に理解し、同様問題で出題形式が変更されても対応できるようすることが大切です。
また公式に関しては極力記憶しました。
公式そのものを問われることもありますが、直接公式を問われてない時でも書き出してみると各変数の影響をイメージする役割に使えます。
あると有利な知識・能力
公害防止管理者試験には持っていると有利となる能力もあります。
化学の知識
窒素や硫黄、リン化合物の特性、pHなど一般的な化学知識はもちろん必要となります。
特に水質1種に関しては無機化学の視点から各元素化合物のクセが分かっていると覚えやすく有利です。
有機化学の知識がある方は化合物名から物性を予測するのに役立ちます。
更に分析化学に関わる溶液調製、分光、イオン化方法、検出器なども直接出題されることもあり、知識や経験がある方は予測がしやすくなります。
ふっ化水素に関する記述として、誤っているものはどれか。
R5 大気有害物質特論 問2
- 常温で無色の発煙性の気体である。
- 水溶液は弱酸であるが、多くの金属を溶解・腐食する。
- 水溶液は、二酸化けい素やけい酸化合物を溶かす性質がある。
- 耐圧容器に詰めて、液体として取り扱われる。
- 空気との混合物は爆発性が高い。
工場設備の知識
集塵機、濾過器、冷却塔、ボイラー、吸収塔など意外と皆さんの工場内にある設備に関する知識が問われることが多いです。
各業種における製造工程に関する問題も出題されることもありますが、未経験業種でも設備から予測をすることができます。
自社工場の設備を見ておくなどしてイメージできるようにしておくと試験で役に立ちます。
汚泥の脱水に関する記述として、誤っているものはどれか。
H30 汚水処理特論 問9
- 真空ろ過では、多孔ドラムにろ材を巻き付けてこれを回転させ、内部を減圧して汚泥をろ布面に吸い付ける。
- ベルトプレスは、汚泥に凝集剤を添加して凝集させ、これを目の粗いベルト状のろ布の上で重力によって脱水し、ろ布上に残った汚泥をそのまま脱水汚泥として排出する。
- フィルタープレスでは、汚泥は加圧ポンプでろ過機の各ろ過室に押し込み、圧搾(あっさく)脱水した後に各ろ板を外し、ケーキを排出する。
- スクリュープレスは、ケージの中で回転するウォームによって汚泥をケージ内の挾隙(きょうげき)部に送りこんで、圧搾圧力によって脱水する。
- 遠心脱水では、高速回転による遠心力を利用して汚泥の脱水を行う。
文章を正しく読む力
公害防止管理者試験には意外と知識が無くても解ける問題が潜んでいます。
条文の内容に対して括弧埋めをする問題に多いのですが、選択肢の中に埋めても話が通じない(文章がおかしい)ことがあります。
どうしても分からない場合には話の流れから自然な選択肢を選ぶこともありです。
論理的思考力
試験難易度の項目でも述べましたが、合格の近道は広い知識を持つことで難解問題を予測して解けるようになることです。
そのためにも持っている知識・経験から論理的に推測して答えを導く必要があります。
このような能力がある方は合格率が大きく上がります。
まとめ
試験の合格率は20~30%程度、一発合格者に絞れば合格率は10%以下です。
過去問の勉強は「公害防止管理者試験まとめました」というサイトがオススメです。
以下に注意しながら勉強して下さい。
- 環境省のサイトは見ておく
- 自社の設備を見ておく
- 関係法令は何度も読んでおく
- 話の流れや論理的に正しいと思う答えを選ぶ