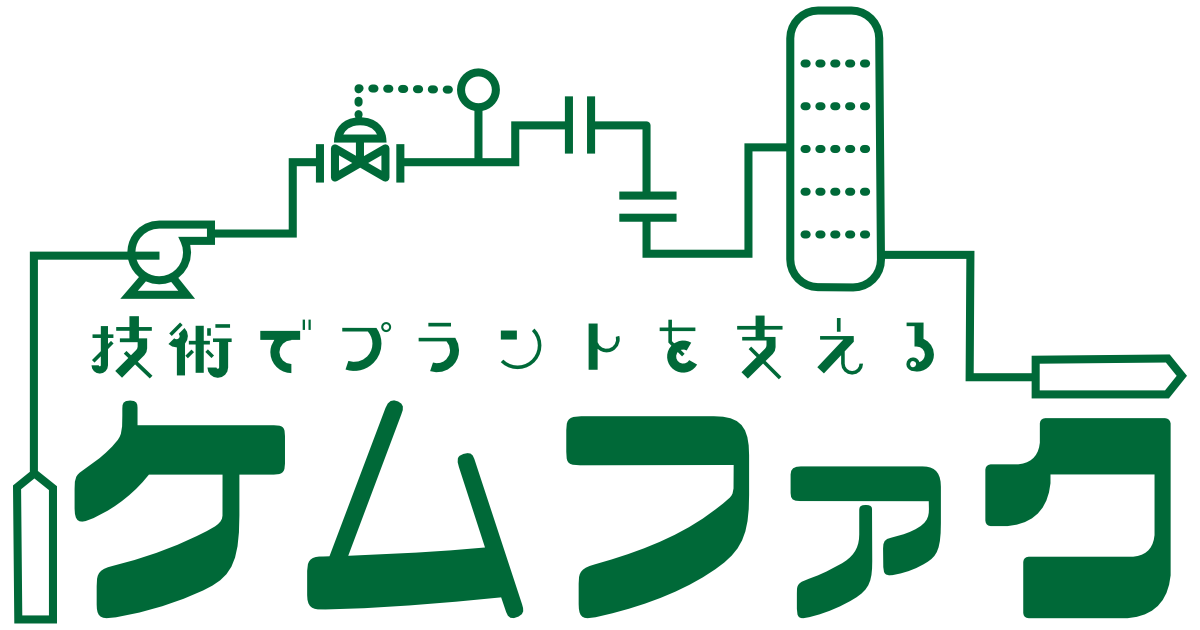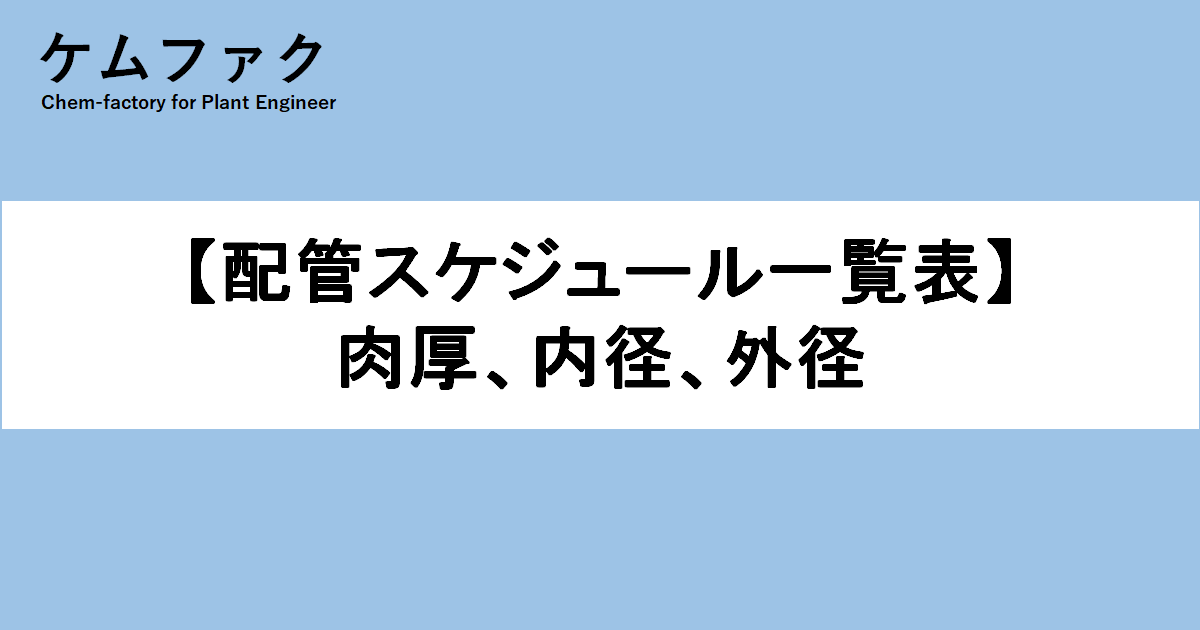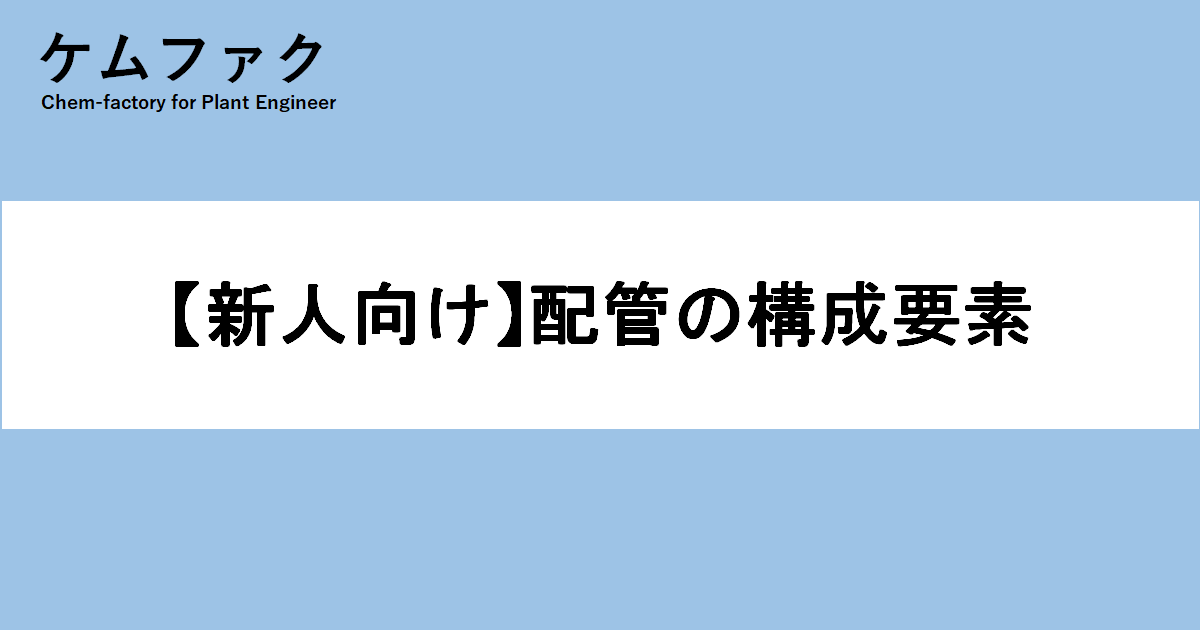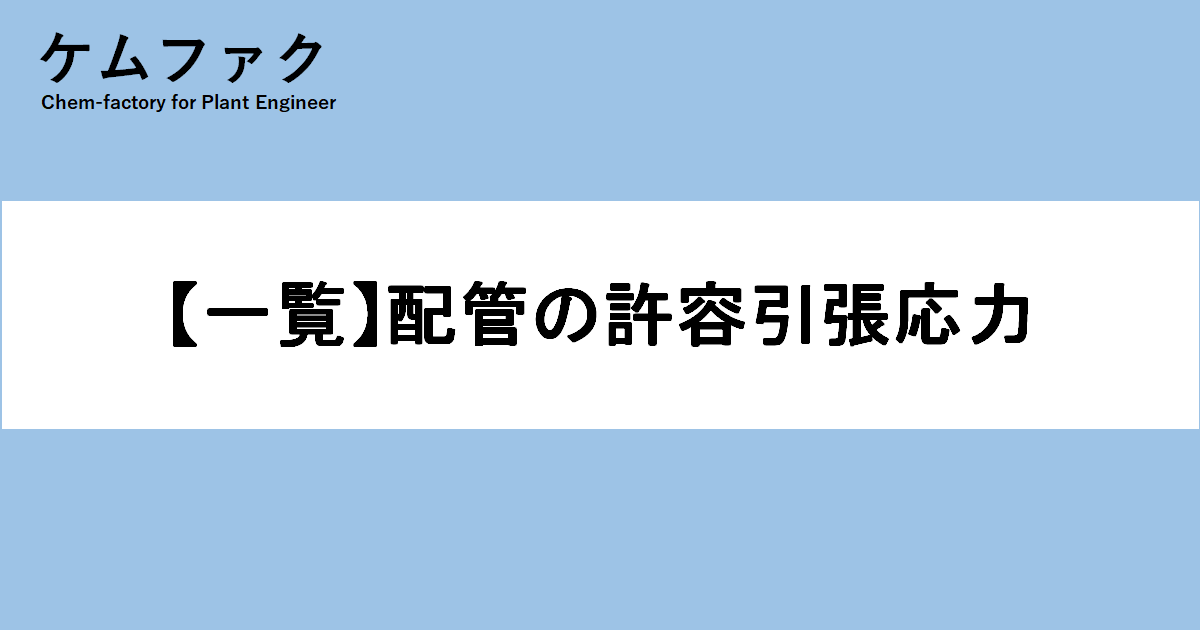パイプの仕様は主に材質と呼び径で決まります。
呼び径は配管外径の規格値をキリの良い数字で表現したものです。
その中でもA呼称とB呼称の2種類があり、A呼称は「ミリメートル」での表現、B呼称は「インチ」での表現になります。
| 外形mm | A呼称 | B呼称 |
|---|---|---|
| 10.5 | 6 | 1/8 |
| 13.8 | 8 | 1/4 |
| 17.3 | 10 | 3/8 |
| 21.7 | 15 | 1/2 |
| 27.2 | 20 | 3/4 |
| 34.0 | 25 | 1 |
| 42.7 | 32 | 1 1/4 |
| 48.6 | 40 | 1 1/2 |
| 60.5 | 50 | 2 |
| 76.3 | 65 | 2 1/2 |
| 89.1 | 80 | 3 |
| 101.6 | 90 | 3 1/2 |
| 114.3 | 100 | 4 |
| 139.8 | 125 | 5 |
| 165.2 | 150 | 6 |
| 190.7 | 175 | 7 |
| 216.3 | 200 | 8 |
| 241.8 | 225 | 9 |
| 267.4 | 250 | 10 |
| 318.5 | 300 | 12 |
| 355.6 | 350 | 14 |
| 406.4 | 400 | 16 |
| 457.2 | 450 | 18 |
| 508.0 | 500 | 20 |
呼び径とは
呼び径は配管外径の規格値をキリの良い数字で表現したものです。
A呼称
A呼称は配管外形を「ミリメートル」単位で表した呼び径です。
当初はインチ表記されていましたが、メートル表記が主流になるにつれて別の表現法を求められるようになりました。
それがA呼称です。
B呼称
B呼称は配管外形を「インチ」単位で表した呼び径です。
インチ表現をB呼称として定め、配管外径に近いA呼称が新たに定められました。
呼び径の変換
A呼称、B呼称とそれぞれ呼び方が違いますが、互いに対応する呼び径があります。
例えば25Aは1B、50Aは2Bです。
規格
配管径および肉厚は、JIS規格やASME規格で定められています。
300A(12B)以下の外径はJIS規格とASME規格のサイズが異なりますので注意が必要です。
350A(14B)以上ではどちらの規格も同じサイズになっています。
昔のアメリカの鋼管規格の影響から、300A以下では内径の実寸法に近く、350A以上では外径の実寸法に近くなります。
内径との関係性
呼び径は対応する外径を知ることが出来ます。
そこにスケジュール番号に対応した肉厚を利用することで内径を算出することが出来ます。
配管内径=配管外径-肉厚×2
オススメ書籍
・トコトンやさしい配管の本
まず配管を勉強したいときに必ず読みたい書籍です。新人さんにオススメです。
-

-
トコトンやさしい配管の本
www.amazon.co.jp
・はじめての配管技術
配管の勉強をするために次に読んでおきたい書籍です。
配管継手に関しても一通りのものが解説されています。
-

-
はじめての配管技術
www.amazon.co.jp
・化学プラント配管設計の基本
上記書2冊で基礎を学んだあと、化学プラントで配管設計を行うなら必ず読んでおきたい書籍です。
化学工学も同時に学ぶことができ、内容が充実しています。
-

-
化学プラント配管設計の基本―配管技術者への道しるべ
www.amazon.co.jp