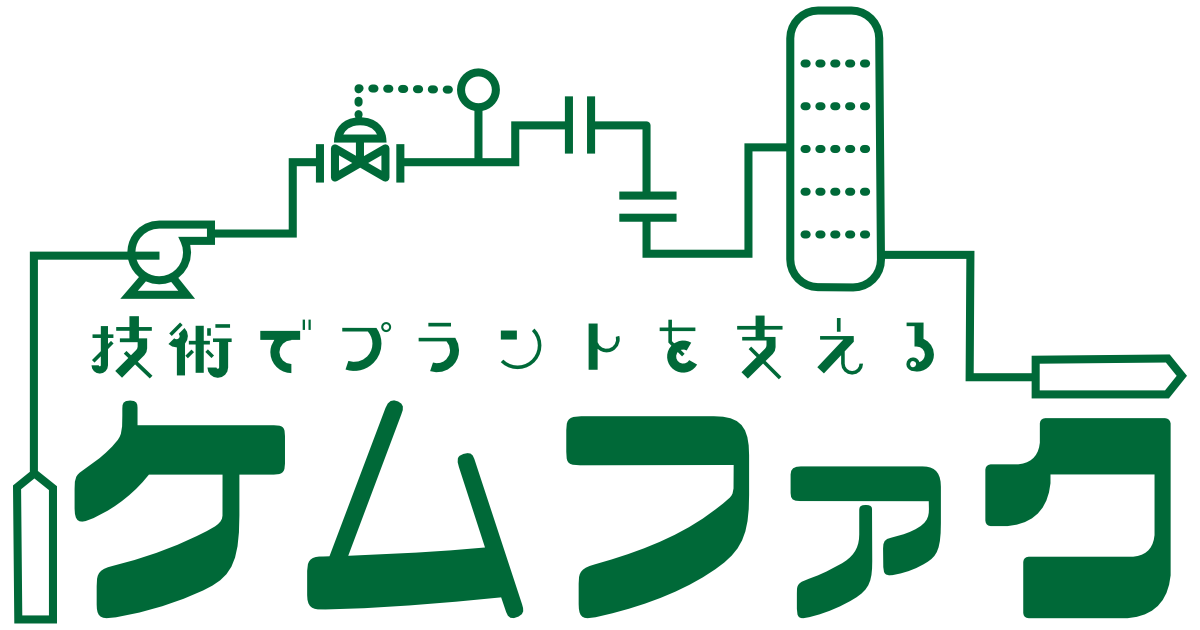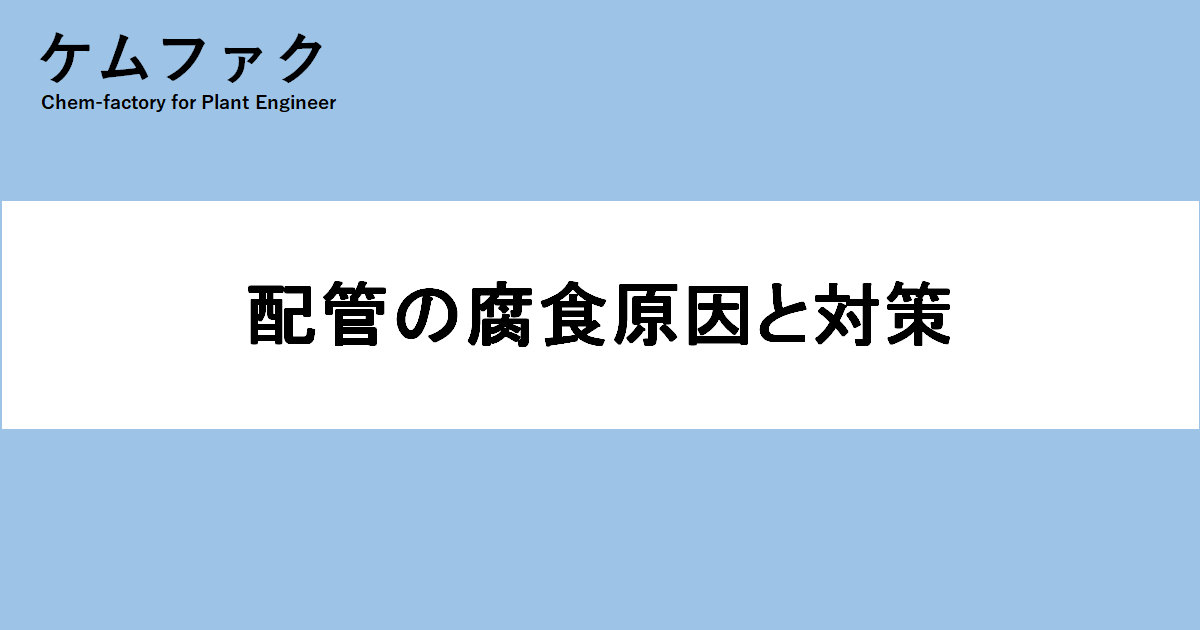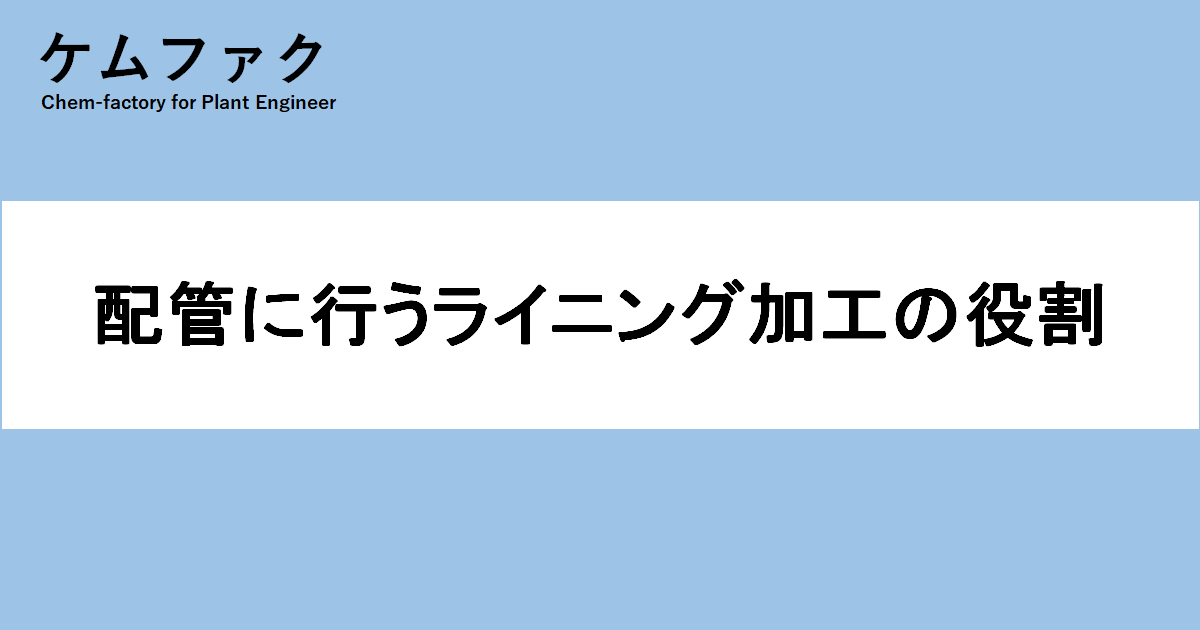錆は金属表面に腐食が発生することを指します。
鉄は安価であり機械的特性や加工性に優れる一方で防食(防錆)の検討が必須となります。
防食(防錆)とは?
錆を防ぐことを防食、もしくは防錆(ぼうせい)と呼びます。
防食には被覆防食、電気防食、耐食材料使用の3種類があります。
根本的な腐食の原因
腐食が起きる根本的な原因は水分と酸素の存在です。
鉄の場合、鉄表面に付着した水分が鉄をイオン化し空気中の酸素と反応して酸化鉄が生成されます。
そのため防食の方法としては以下の2種類があります。
被覆防食
被覆防食は表面を被覆することで金属が酸素や水分と触れるのを防ぎます。
塗装、金属被覆、無機被覆、有機ライニングなどがあります。
塗装
塗装は防錆顔料や着色顔料などを金属に塗り方法、つまりペンキ塗りです。
不動態皮膜を形成したり酸素・水分・塩分などから遮断する役割があります。
特徴としてイニシャルコストが安い反面、塗り直しなどランニングコストがかかります。
特に対候性や物理耐久性には劣ります。
金属被覆
金属表面に金属皮膜を形成します。
後述するライニングに比べて膜厚が薄い特徴があり代表的な方法としてめっきや金属溶射があります。
ランニングコストが低い一方でイニシャルコストが高くなります。
鋼材として有名なガルバリウム鋼板は鋼板にガルバリウム(亜鉛+アルミ+シリコン)をめっきしたものです。
鋼板を亜鉛めっきするとトタン、スズめっきするとブリキと呼ばれます。
溶射は溶融した鉄よりイオン化傾向の高い金属を溶解して吹き付けることで被膜を形成します。
亜鉛やアルミニウムによる溶射が有名です。
金属同士の接触ですので異種金属接触の影響に注意しなければなりません。
無機被覆
金属や無機物質といった無機材料の被膜を溶射・焼き付け・張り合わせなどの方法で金属表面に形成させます。
モルタルによる被覆が代表的ですが現地施工に限られるためイニシャルコストがかかります。
有機ライニング
樹脂やゴムといった有機素材の被膜を溶射・焼き付け・張り合わせなどの方法で金属表面に形成させます。
塗装よりも膜厚が2~3倍程度厚いことが特徴です。
特にポリエチレンライニングが代表的で安価に入手できることから配管材料としてもよく活用されています。
電気防食
金属に電極を接続し、電気を流して金属の電位をイオン化が起こらない水準まで変化させます。
主に被覆防食が行いづらい海洋や土壌などで採用されます。
流電陽極法(犠牲陽極法)と外部電源法があります。
流電陽極法(犠牲陽極法)
流電陽極法(犠牲陽極法)は 鉄よりもイオン化傾向の高い亜鉛やアルミニウムなどと電線で接続することで防食を行います。
外部電源が必要ないため比較的活用しやすい方法です。
被覆防食よりも性能は良いのですがイニシャルコストが高いこと、電極配置不足で防食不良が起きる可能性もあることが難点です。
外部電源法
電極には耐久性電極を用いて外部から直接電流を流すことで電位を変化させます。
外部電源が必要になってしまうデメリットがありますが長期で利用ができるメリットがあります。
また外部電源を使用することから周囲への影響も考慮する必要があります。
耐食材料使用
耐食材料は金属に添加物を加えて不動態皮膜を形成させます。
代表的な鉄の耐食材料としてはステンレス鋼が挙げられます。
ステンレス鋼
ステンレス鋼は鉄合金中のクロムが不動態皮膜を形成する役割を主に担っています。
その他にもニッケルやモリブデンを含むステンレス鋼は更に耐食性が強化されます。
例えばSUS304には約18%のクロムが含まれており、SUS316にはクロムに加えて約2%のモリブデンが含まれています。
イニシャルコストは高くなりますが、低いランニングコストを優先するために塗装した鉄材よりもステンレス鋼を選択する場合もあります。
オススメ書籍
・改訂版 自主保全士公式テキスト
設備保全に関する体系的な知識が得られます。
公式テキストには充実した解説があり、試験を受けなくとも勉強すれば相当力が付きます。
-

-
改訂版 自主保全士公式テキスト 検定試験&オンライン試験対応
www.amazon.co.jp
・一番最初に読む機械保全の本
機械保全について基礎の基礎が学べる書籍です。
写真やイラストが多いため初心者にオススメできます。
-

-
一番最初に読む機械保全の本
www.amazon.co.jp
・機械要素設計 (JSMEテキストシリーズ)
機械要素の特徴を理解し、どのように設計すべきか学べます。
機械を利用する側として、使い分け方を知っているだけで設計の幅が広がります。
-

-
機械要素設計 (JSMEテキストシリーズ)
www.amazon.co.jp