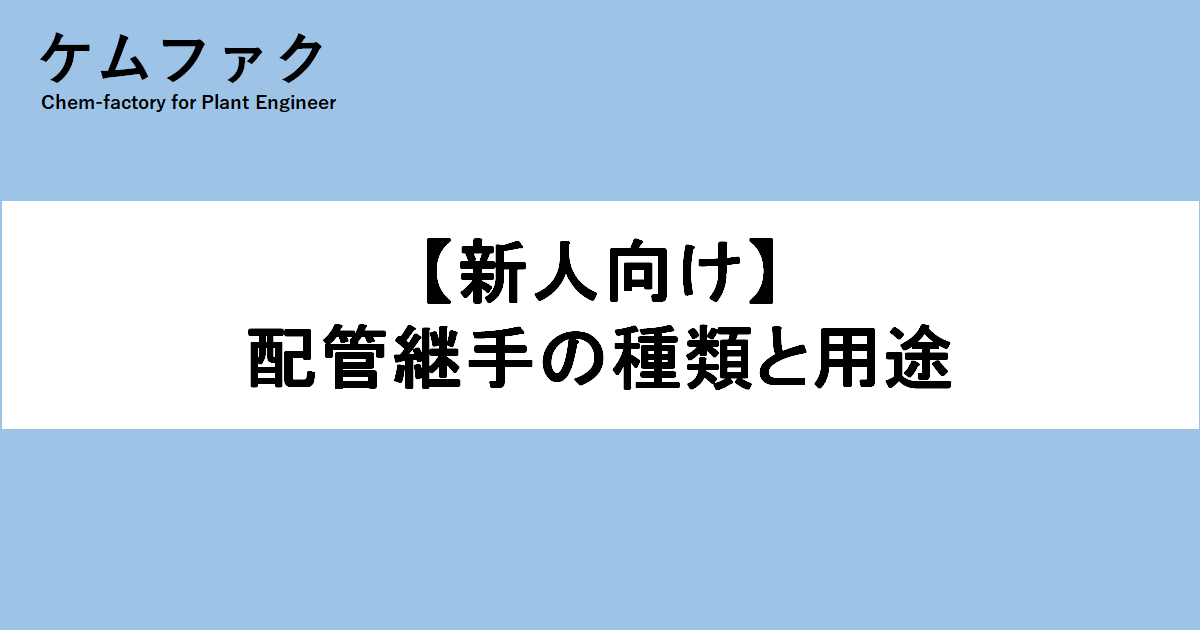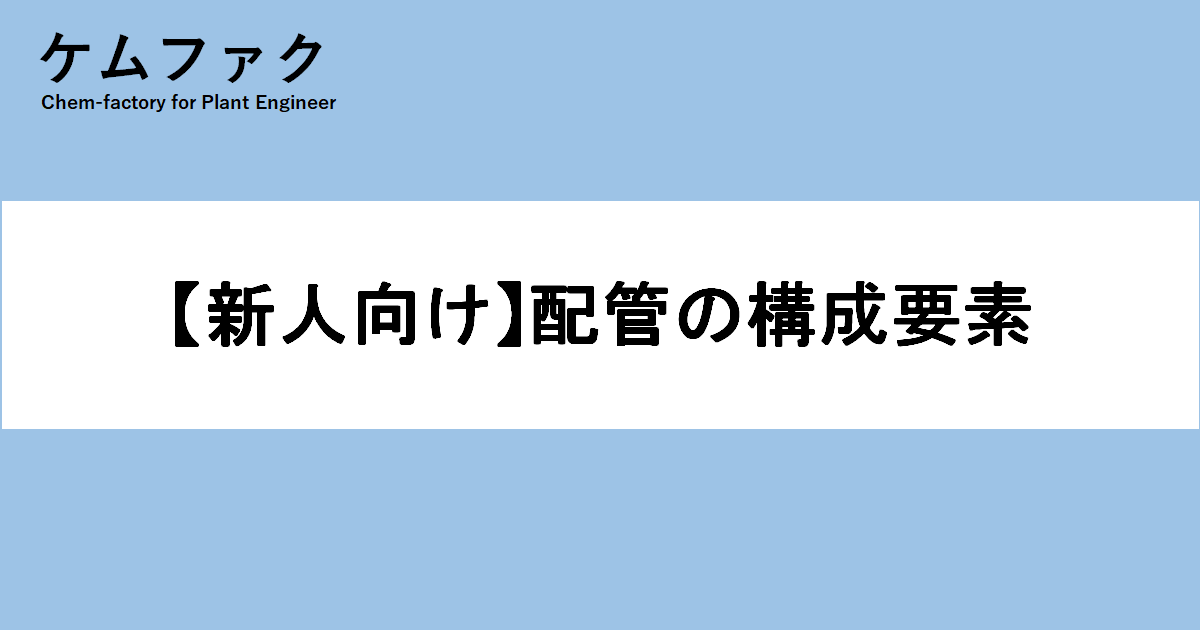流体配管では基本的にエルボ、特に圧力損失の少ないロングエルボが使用されます。
| 条件 | 使用 |
|---|---|
| 圧力損失を減らしたい | ベンド |
| 入手しやすさ | エルボ |
| 流体配管での使用 | エルボ |
| 電線管への使用 | ベンド(断線を防ぐ) |
| 自在に曲げ半径を決めたい | マイターベンド |
違いや使い分け
いくつかの方向からエルボとベンドの使い分けを見ていきます。
圧力損失
エルボとベンドのうち、ベンドの方が曲げ半径が大きく流体は緩やかに曲がることができます。
そのためベンドの方が圧力損失は小さくなります。
配管サイズ50A程度までは大きな差はありませんが、100A程度になるとエルボの圧力損失はベンドの約1.5倍になります。
ちなみにエルボの中にも外径Dに対して曲げ半径が1.5Dのロングエルボ、1.0Dのショートエルボと2種類存在します。
一般的には圧力損失の少ないロングエルボが使用されます。
市場流通量
一般的に配管流路を曲げようとする際はエルボが選択されます。
そのため市場流通量としてはエルボの方が多くなります。
広いサイズで入手しやすいことを理由にエルボを選択するのもありです。
利用用途
流体用の配管はエルボが一般的に使用されます。
ただし電線管のようなケーブルを通すような配管にはベンドが用いられます。
電気工事のやり方として、電線管を取り付けてから中にケーブルを通すやり方で施工するためです。
極力曲げ半径が大きなベンドを選択して配線しやすくしています。
またケーブルに極端な曲げの力がかかって断線するのを防ぐ役割もあります。
マイターベンド(エビ管)の使いどころ
マイターベンドは斜め切りした短い鋼管を繋げて作るベンドでエビ管とも呼ばれます。
配管径が非常に大きく適当なエルボやベンドが無い場合に使用されます。
また自在に曲げ半径を設定することができる特徴があります。
ただし複数の交換を溶接して繋げるために1つのマイターベンドには複数回の溶接と検査が必要となります。
この手間によりコストは高くなってしまいます。
溶接部が多く応力が残りやすいため350℃、15kg/cm2程度までの使用範囲となっています。
オススメ書籍
・トコトンやさしい配管の本
まず配管を勉強したいときに必ず読みたい書籍です。新人さんにオススメです。
-

-
トコトンやさしい配管の本
www.amazon.co.jp
・はじめての配管技術
配管の勉強をするために次に読んでおきたい書籍です。
配管継手に関しても一通りのものが解説されています。
-

-
はじめての配管技術
www.amazon.co.jp
・化学プラント配管設計の基本
上記書2冊で基礎を学んだあと、化学プラントで配管設計を行うなら必ず読んでおきたい書籍です。
化学工学も同時に学ぶことができ、内容が充実しています。
-

-
化学プラント配管設計の基本―配管技術者への道しるべ
www.amazon.co.jp