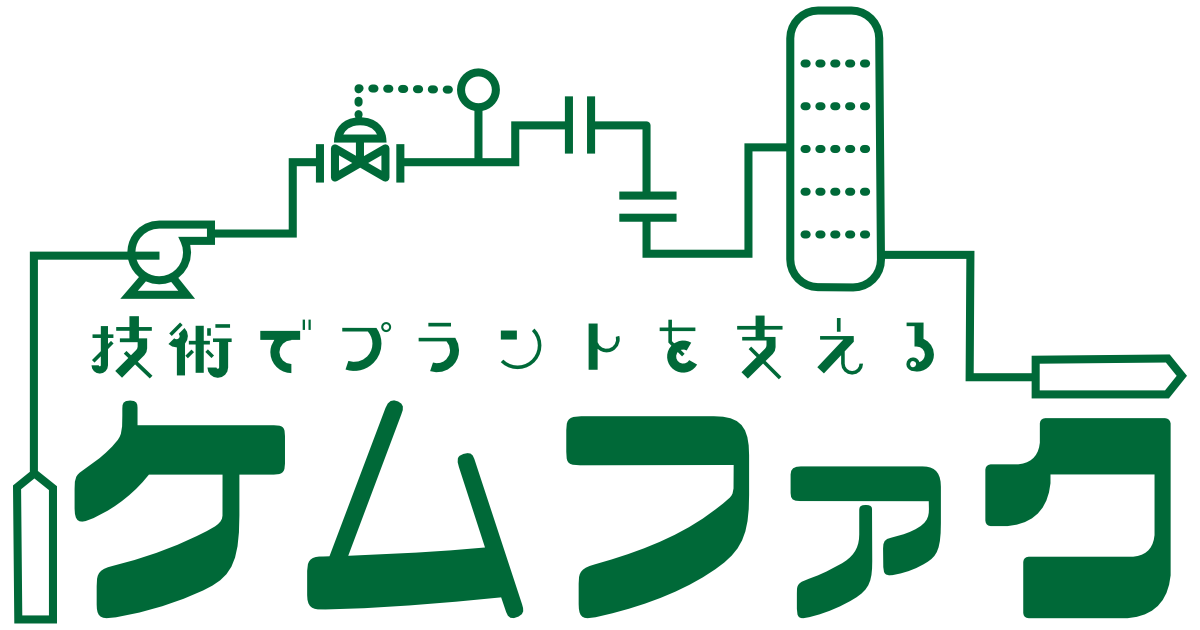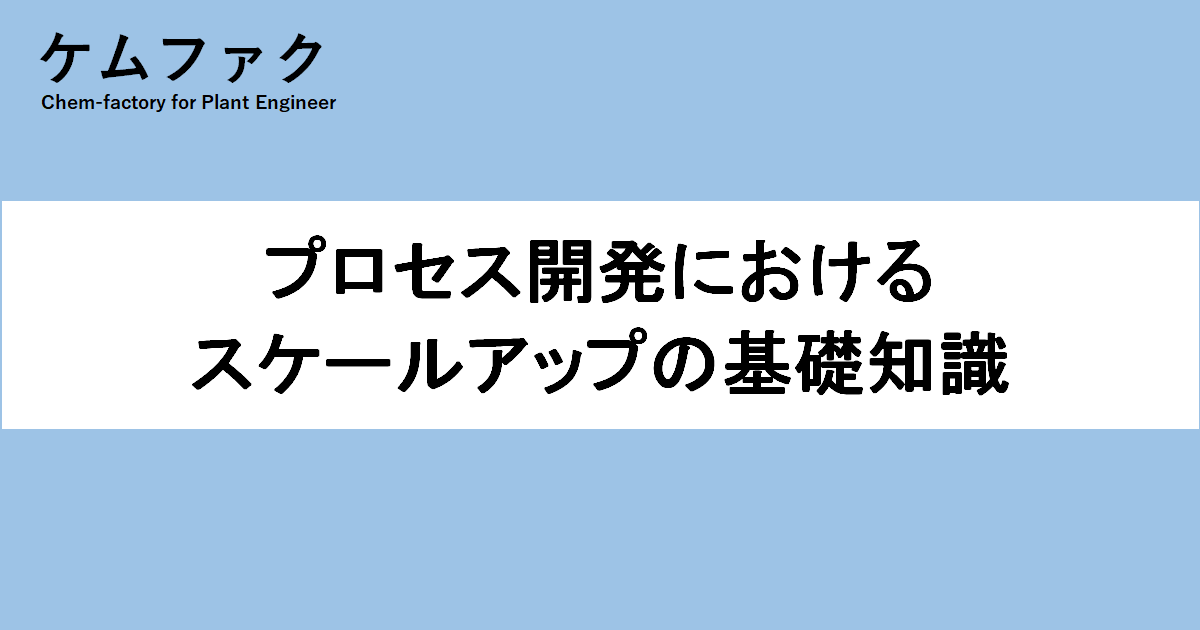流れの状態
運転方式の違いはプロセス中の流れの違いに繋がります。
まずは2つの流れの状態について解説します。
定常
定常な流れは操作条件が一定に保たれている状態を意味します。
いわゆる安定した状態です。
操作条件とは例えば温度、圧力、流量、組成が代表的な要素です。
非定常
非定常な流れは操作条件が変動している状態を意味します。
時間とともに変化するため、時系列もしくは複数時点でのデータを確認しなければ製造の状況が把握できません。
バッチ式と連続式
まずはバッチ式と連続式の基本概念を解説します。
その後に条件に応じた使い分けを深掘りしていきます。
バッチ式
バッチ式の運転は、装置内の内容物を毎回全て入れ替える運転方式です。
回分式とも呼ばれます。
1サイクルごとに中身が全て入れ替わるため、流れが非定常になります。
例えばファインケミカルや医薬品、食品などの業界で採用されています。
連続式
連続式の運転は、一定速度で連続的に操作する運転方式です。
この場合はまず定常な流れを作ることから始まります。
運転管理においては、気温をはじめ外部の変化を受けながら操作条件を一定に保つことが求められます。
例えば石油精製や石油化学などの業界で採用されています。
条件に応じた使い分け
バッチ式、連続式どちらにもメリットデメリットがあります。
そのため条件に応じた使い分けを解説します。
生産する量と種類
バッチ式の運転方式は品種の変更が頻繁に発生する場合に効果的です。
特に異物の混入や微生物の発生を嫌う医薬品や食品は、厳重な洗浄を行います。
そのような場合はたとえ大規模生産であってもバッチ式が採用されることがあります。
その都度、装置内をクリアに出来るのがバッチ式の良い点です。
一方で同じ製品を大量に製造する場合は連続式が効果的です。
バッチ式に比べ手間がかからず安定した品質を確保しやすいことも特徴的です。
装置の役割
バッチ式では1つの装置が複数の工程を担うことができます。
装置数を抑えられることから、狭い工場内でもスペースを確保できます。
例えば1つのタンクでも以下の工程を行えます。
- 加熱昇温
- 反応
- 分離(白土脱色など)
上記工程は順番に行う必要があり、連続的な製造はできません。
連続式を目指す場合は、各工程ごとに装置を分ける必要があります。
製品の区切り
バッチ式の場合は使用材料や製造条件などはバッチ毎に正確に把握できます。
データを解析して品質を向上させる観点からも扱いやすくなっています。
一方で連続式の場合は区切りが少し曖昧です。
連続的に製造するとはいえ、途中で原料の追加供給は発生します。
ただし流れを止めたり定常から非定常に変わるのを防ぐことから、原料を追加供給しながら運転します。
そのためグラデーションを描きながら追加原料の比率が増加します。
品質に異常が発生したとき、どこからが原料追加したときの製品なのか正確には把握できません。
そのため常に工程内の状況を監視できることが重要です。
オススメ書籍
・反応工学
反応工学や触媒化学を学ぼうと思ったらこの書籍です。
これを読めば基礎は十分身に付きます。
そして何より例題や演習問題、解答解説が十分に盛り込まれている点もオススメできる理由です。
-

-
反応工学
www.amazon.co.jp
・化学工学ー解説と演習ー
化学工学を勉強したい!と思ったら真っ先にオススメしたい書籍です。
他の汎用化学工学書籍には無い「撹拌動力計算」や「撹拌伝熱計算」も記載されています。
-

-
化学工学―解説と演習ー
www.amazon.co.jp
・化学プラント配管設計の基本
伝熱の種類、熱伝導の計算、熱交換器の種類について記載されています。
その他、化学工学の基本事項が解説された後、それらを踏まえて化学プラントにおける配管設計の基礎から詳細に解説される書籍です。
この1冊で配管設計を一通り勉強できます。
-

-
化学プラント配管設計の基本―配管技術者への道しるべ
www.amazon.co.jp