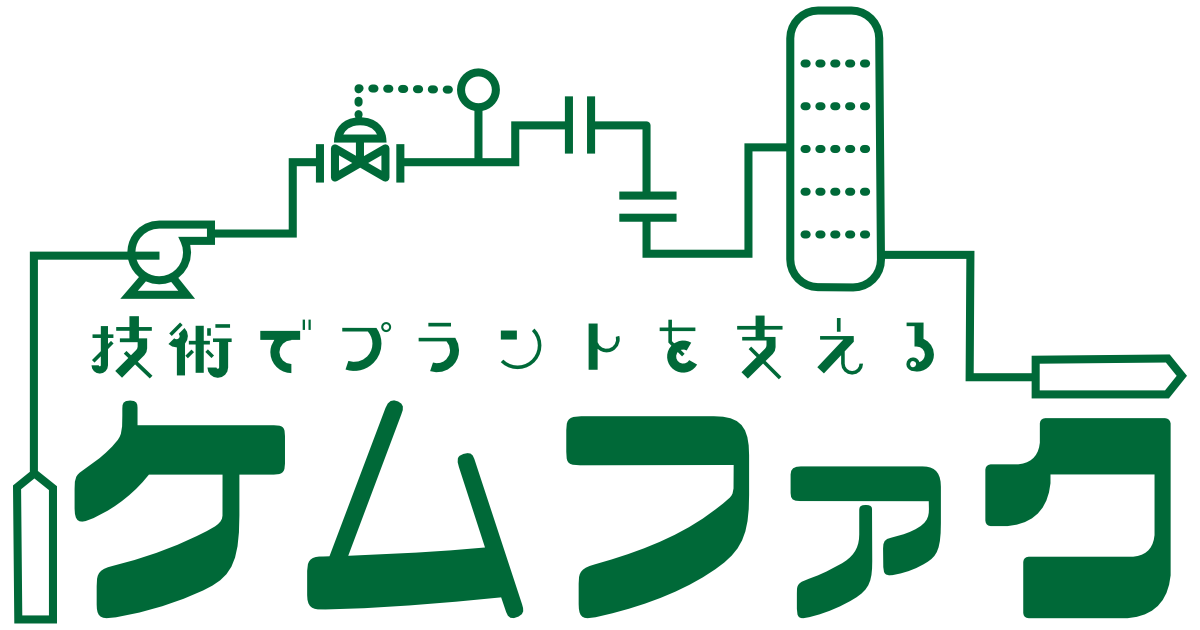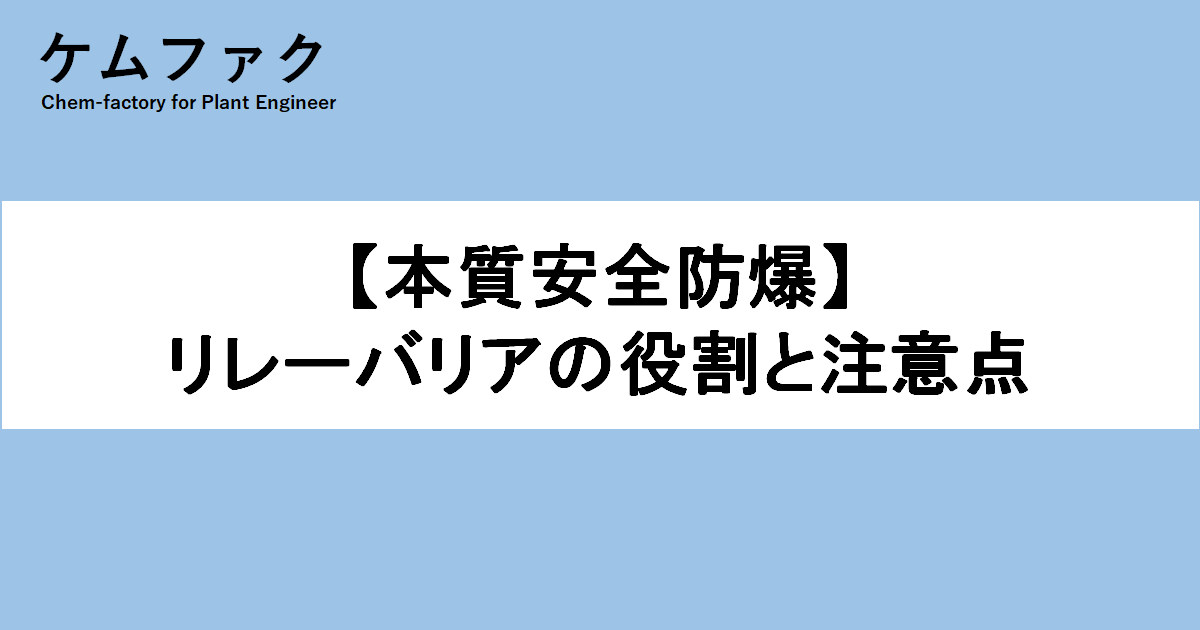(事前知識)防爆とは?
そもそも防爆規格は電気設備を爆発危険性場所で使用できるように定められたものです。
つまり電気設備に起因する接点火花や短絡などが原因となりガスに引火して爆発するのを防ぎます。
危険場所のクラス分け
爆発危険場所と言っても常にガスが発生する場所、異常時のみ発生する場所など状況は様々です。
そのため爆発性雰囲気の発生状況に応じて危険場所は以下の3クラスに分けられます。
- ゾーン0 通常状態で連続的もしくは長期間発生する場所(引火性液体の液面付近など)
- ゾーン1 通常状態で発生する可能性がある場所(タンクの点検口など)
- ゾーン2 異常状態で生成する可能性がある場所(フランジ接合部の劣化箇所など)
防爆構造の種類
危険場所のクラスや爆発対策によって様々な防爆構造が考案されています。
モーターにおいては安全増防爆構造と耐圧防爆構造が主に採用されています。
防爆構造の詳細に関しては日本電熱株式会社のHPに分かりやすく記載されています。
安全増防爆構造は通常使用において温度上昇したりアークや火花などが発生したりしないよう安全度を増した構造です。
耐圧防爆構造は内部で爆発しても容器が耐え、外部に引火しないようにした構造です。
防爆構造による違い
ここでは実際にモーターにおいてどのような対策がされているか違いを解説します。
使用可能エリアの違い
既に爆発危険場所はゾーン0, 1, 2の3つに区分されていることを解説しました。
実は耐圧防爆構造はゾーン1, 2で使用可能ですが、安全増防爆構造はゾーン2でしか使用できません。
つまり耐圧防爆モーターの方が危険なエリアで使用できる規格です。
安全増防爆モーター
モーターは内部損失による温度上昇が著しい場合に絶縁物を劣化させる恐れがあります。
そのためJIS C 4210にて耐熱クラスが設けられ、対応する温度上昇限度が定められています。
温度上昇限度は容器外面温度と周囲温度の差を表し、周囲温度が40℃を超える場合は超過温度分の温度上昇限度が減少します。
安全増防爆モーターは巻線の温度上昇限度を低く設定されています。
その他にも導電体同士の距離である絶縁距離(沿面距離や絶縁空間距離)を大きくとっています。
また端子箱のふたのねじは特定の者のみ開けられるよう錠締め構造になっています。
錠締め構造ではボルトの頭部周囲に板やキャップなどが溶接接続されており工具が回せないようになっています。
耐圧防爆モーター
耐圧防爆モーターは爆発の衝撃に耐える必要があるため、各部品の肉厚を上げています。
更に爆発等級に応じてはめ合い面や接合面などの寸法や精度が決まります。
爆発等級は化合物ごとに定められており、爆発の破壊力により分類するものです。
つまり耐圧防爆モーターは頑丈かつ精巧に作られているため高コストなモーターとも言えます。
また耐圧防爆モーターも安全増防爆モーターと同様に錠締め構造となっています。
オススメ書籍
・現場エンジニアが読む 電気の本
電気の基本理論から始まり、測定機器や電子部品、制御機器など基本的な要素が解説されています。
-

-
現場エンジニアが読む 電気の本(第2版)
www.amazon.co.jp
・現場エンジニアのための電気の実務がわかる本
動力回路や制御回路の設計、トラブルシューティング、保全など電気に関する現場向けの解説がされています。
-

-
現場エンジニアのための電気の実務がわかる本―もう現場でつまずかないズバリ答える50の疑問!
www.amazon.co.jp
まとめ
今回はモーターの安全増防爆構造と耐圧防爆構造の違いを解説しました。
実際に使用するときはそれほど気にすることはありませんが知っていて損はありません。
防爆構造の1つとして一番厳しいゾーン0でも使用できる本質安全防爆構造があります。
本質安全防爆構造に関連するリレーバリアについて以下で解説していますので宜しければご覧になってください。